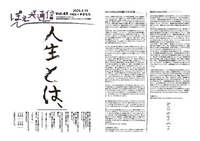めがね橋

千本松大橋の由来と魅力
大阪市の木津川に架かる千本松大橋は、その独特の形状から「めがね橋」とも呼ばれる巨大なループ橋です。この橋は、なぜこのような形になったのでしょうか?また、この橋の近くには、現在も渡し船が運行しています。千本松大橋の由来と魅力について、探ってみましょう。
千本松大橋の由来
千本松大橋は、1973年(昭和48年)に完成した橋で、全長は1228.3m、幅員は9.75m、主橋梁部はL=323.5m(78.0m+150.0m+95.5m)です。桁下の高さは水面から33mあります。この高さは、木津川を航行する大型船に配慮したものです。当時、木津川沿いには工業地帯や造船所が広がり、大阪市内有数の産業拠点となっていました。しかし、陸上交通は不便で、自動車は遠く市の中心部まで迂回しなければならなかったのです。この状況を改善するために、千本松大橋が建設されたのです。
しかし、千本松大橋が完成した同年には、第一次オイルショックや景気の悪化などの影響で、造船所や工場が衰退しました。その結果、千本松大橋の完成と同時に、航路高が33mも必要とする大型船の航行はなくなってしまったのです。
千本松大橋の名前は、江戸時代にこの地の木津川堤防に沿って多くの松が植えられていたことに由来しています。その松は明治時代に伐採されましたが、その名残を留めています。
千本松大橋の魅力
千本松大橋は、車道と歩道があり、自動車や歩行者にとって便利な交通路となっています。また、その特徴的な形状から、「めがね橋」という愛称で親しまれています。両端部の2階式螺旋状坂路(720度ループ)を含めて道路長は1228mありますが、実際に渡る距離は約300mです。しかし、高さ36m(ビル12階相当)まで上ることになるため、歩行者や自転車にとっては所要時間や体力面で負担がかかります。
そこで、千本松大橋の近くには、現在も渡し船が運行しています。千本松渡船場は従来から木津川を渡る歩行者や自転車の移動に利用されてきました。当初は千本松大橋の開設に伴い廃止される予定でしたが、「橋ができても不便だ」という住民の声を反映して存続されました。現在は、大阪市が管理・運営しており、料金は大人50円、小人30円です。渡船は約1分で渡りますが、橋の下を通るときには頭を下げなければなりません。
千本松大橋と渡し船は、木津川の両岸を結ぶ異なる交通手段ですが、共存しています。千本松大橋は、工業化の時代に生まれた橋であり、渡し船は、江戸時代から続く伝統的な交通手段です。この二つの対照的な存在が、木津川の風景に彩りを添えています。
千本松大橋は、大阪市の建設局道路河川部橋梁課が管理しており、浪速の名橋50選にも選ばれています。千本松大橋にアクセスするには、OsakaMetro四つ橋線北加賀屋駅から徒歩約27分か、大阪シティバス「千本松西詰」「南津守二丁目」「南津守」から乗車できます。千本松大橋を渡ってみたい方は、ぜひ足を運んでみてください。
参照
(1) 千本松大橋 - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E5%A4%A7%E6%A9%8B.
(2) 千本松大橋(せんぼんまつおおはし) - 大阪市公式ホームページ. https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000023565.html.
(3) 千本松大橋 渡し舟と共存する、巨大な「めがね橋」【大阪市 .... https://bridgeist.thebridge.co.jp/senbonmatsuohashi/.
(4) 大阪市・大正区の「巨大橋」を“徒歩”と“渡し船”で空中 .... https://www.travel.co.jp/guide/article/29729/.